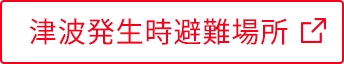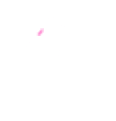へんな生きもの研究所で飼育中のヨロイウミグモ(熊野灘の水深200~300mに生息)、つぶらな瞳(眼点)がキュートです(笑) 本種はイソギンチャクの体壁に吻を挿し、その体液を餌にしています。それで、へんな生きもの研究所では
投稿者: もりたき
イッスンボウシウロコムシ№11、ひきこもる
去年の12月に熊野灘の水深280-400mの深海からやってきた№11(当時、種名はまだ極秘扱いでした) ジンゴロウヤドカリと共生するヒメキンカライソギンチャクの体壁で発見、これが№11との初めての出会い(矢印) でも、表
レモンスズメダイとリュウキュウスガモ
シーグラス水槽ではジュゴンが好む海草(主にリュウキュウスガモ)を展示していますが、少し前に厚く敷いた底砂に大きく陥没したような穴ができていることに気付きました。穴は私の手のひらほどの大きさ。 水槽掃除をする際に誰かが掘り
シマフグが入館しました
水族館の近くで釣りをしていた人からシマフグをいただきました。 シマフグは年に数回程度は搬入されるので、それほど珍しい種類という訳ではありませんが、なかなか綺麗で、個人的にフグの中ではまぁまぁ好きな種類です。 さっそく展示
オウムガイの殻の黒いスジ
オウムガイを飼育すると、水槽の中で新しく作られた殻に黒いスジができます。野生ではツルツル・スベスベなんですけどね。 画像はパラオオウムガイ№97 成長した殻にだけ黒いスジができています。 黒いスジができるはっきりした理由
テンプライソギンチャク近況
テンプライソギンチャク はノリカイメンの一種と共生する珍しい生態を持つイソギンチャクです。 鳥羽を含めた3地点からしか報告されていないこともあり、へんな生きもの研究所では水族館向かいの菅島の磯で採集したテンプライソギンチ
ダイオウグソクムシとオオグソクムシの目について
ダイオウグソクムシとオオグソクムシについて質問を頂きました。目の形に違いはありますか?どちらの方が光に強い、弱いなどありますか?等々… ちなみにオオグソクムシの仲間は世界中の深海から20種ほど知られていますが、そのうちの
え!オオグソクムシが!
今年の夏休みはどういうわけかオオグソクムシやダイオウグソクムシに関する質問をたくさん受けます。 その中で一番驚いたのは、自宅でオオグソクムシを飼育している会社員の方からのものでした。 この方は5月下旬にペットショップでオ