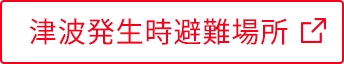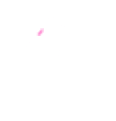先日、最近頻繁に菅島の漁師さん(幸進丸)からヤギやトゲトサカ類(八方サンゴ類)をいただくので、伊勢志摩の海ゾーンのヤギ水槽が華やかになっています、と紹介しましたが、そんないただいたヤギの中に見慣れない種類が一つ。 …何だ
投稿者: もりたき
エダミドリイシ北上中?
先日、生物の買い付けに出かけてきました。場所は三重県の志摩半島の先端にある御座という集落。 漁師さんが取り置いてくれた魚類やカニやヤドカリなどの無脊椎動物をまとめて買い付けます。 漁師さんからいただいた生物の中に見かけな
トゲトサカに隠れる小さなカニ
最近頻繁に菅島の漁師さん(幸進丸)からヤギやトゲトサカ類(八方サンゴ類)をいただくので、伊勢志摩の海ゾーンのヤギ水槽が華やかになっています。 さて、前回いただいたのは、立派なトゲトサカ類。伸びると高さ40㎝以上にはなりそ
感謝状をいただきました
先日、日本動物学会第94回山形大会の席で感謝状をいただきました。 これは ・鳥羽水族館がオウムガイの長期飼育と繁殖において成果を上げ、得られたオウムガイ胚の標本を提供して世界的に例のない複数の研究に貢献したこと ・ダイオ
タイプ標本しか存在しない新種
先日、水族館の生物採集で見つけた新種生物話題を軸に、テレビに出演させていただきました(興味のある方は「森滝 深海」あたりで検索してみてください)。その中でエビノユタンポ Pleonobopyrus kumanonaden
立ち上がるチョコチップ
コーラルリーフダイビングゾーンを入ってすぐの水槽にコブヒトデがいます。私は勝手に「チョコチップ」と呼んでいますが、このコはこの水槽を設置した頃からいるので、もうかれこれ水族館暮らしも12年ほどになるでしょうか。 昔は小さ