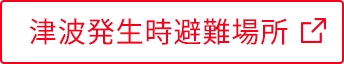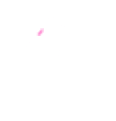へんな生きもの研究所のアパート水槽7号室のヨコエビBathyceradocusの続きです。 とても珍しい種類である可能性が高く、現在、研究者に調べてもらっていますが、結果が出るまで、水族館としてできることはないかと水槽内
投稿者: もりたき
サンゴが美しく育っています
昨年12月に沖縄の八重山から搬入したミドリイシの仲間(サンゴ)を水槽に展示したと紹介しましたが、その後の変化です。 最初の頃は全体が茶色がかっていて、あまりきれいではなかったのですが、最近は調子良く成長して色揚がりも上々
パラオオウムガイB12が孵化しました
パラオオウムガイのベビーラッシュはまだまだ続いていますよ~!今朝12個体目となるB12が誕生しました。これで現在の飼育数は8匹になりました(B1、B4、B5、B6は死亡) 数日前から卵の向きが変わる(孵化直前の胚が卵殻の
孵化から2ヶ月経ったので
パラオオウムガイB2とB3を孵化専用水槽(23℃)から成体の展示水槽(17℃)へ移動しました。 オウムガイの仲間は高い水温で産卵し、孵化後しばらくして親と同じ水温の海域へ沈降すると考えられているので、水族館ではこれまでの
7号室のBathyceradocusヨコエビ
へんな生きもの研究所のアパート水槽7号室でひっそりと飼育中のヨコエビBathyceradocus sp.(熊野灘の水深350mで採集)。まだ名前が付けられていない種類(未記載種)である可能性が高いので、現在、研究者に調べ
2号室のチュウコシオリエビの仲間
今更ですが… へんな生きもの研究所にあるアパート水槽は幅40㎝の水槽が全部で30基並んでいます。冷水系(10℃)、温水系(18℃)、暖水系(25℃)がそれぞれ上下5基の10基ずつ。 これまで飼育日記では個々の水槽を展示生
ヤドリニナのベリジャー幼生
先日書き込んだヤドリニナ(巻貝)に寄生されたウニの続きです。 見ると、どうも体の動きが悪いようす(寄生の影響?)水槽から取り出して状態を観察してみることにしました。しばらく観察していると… 米粒のような卵嚢からヤドリニナ
珍ヨコエビの生態観察
へんな生きもの研究所で飼育中のヨコエビBathyceradocus sp.の正体を研究者に調べてもらっています(熊野灘の水深350mで採集) 現在、シロウニ水槽の中に入れた沈木の、中央あたりの窪みに6匹(大1・中4・小1